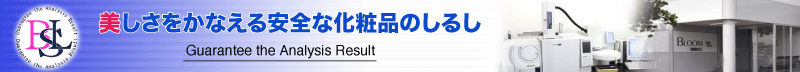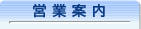 |
|
|
| 化粧品の配合成分表示ラベルと薬事法の成分規制について。 |
|
|
|
|
| 成分の分析方法と検査料金。民間ならではの納期・料金で。 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
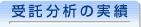 |
| 試験検査の依頼をさまざまな企業や団体から受託しています。 |
|
 |
|
|
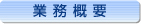 |
|
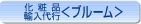 |
|
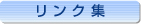 |
|
 |
|
|
 |
|
| 化粧品は肌に直接つけるものですから「あなたのここち良さ」と「科学的な安全の根拠」の両方があってこそ、化粧品本来の役割が果たされます。成分分析を行うわたしたちのQ&Aを、あなたに合った化粧品選びのためにお役立てください。 |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
例えば、ホルマリンやカドミウム化合物など。
薬事法で配合が全面的に禁止されている成分。
この成分は配合禁止である以上は表示はありませんから、ふだんは知る機会はないでしょう。 |
|
 |
|
例えばパラベン(防腐剤のひとつ)や一部の色素。
一定の前提条件のもと、薬事法で配合が制限されている成分。
しかし、これらの成分は製品の品質維持に必要だったり、「彩り」に欠かせなかったりします。
もちろんこれらの成分を配合しない製品はありますし、配合しないメリットもあります。同時に、配合しないデメリットもあるでしょう。
ですから、成分単体ではなく製品全体としてのメリットとデメリットを理解する必要があると思います。 |
|
 |
|
薬事法の規制の有無にかかわらず、使ったひとの肌に合わず、肌にトラブルが起こる成分。
しかし、特定のひとに対してどの成分がどんなトラブルを起こすかはひとそれぞれです。
肌へのストレスを感じたら、製品の「成分表示」と照らし合わせて専門医に相談しましょう。 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
使い心地の良さ。
肌に合うか、肌荒れなどトラブルがないか、好みの色や香りか等。つまり「あなたが気持ちよく使える」こと。 |
|
 |
|
安全に対する科学的根拠。
薬事法に準拠して製造・販売されている製品であること。ならびに、準拠の事実を公に示せる製品であること。 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
以下の条件をすべて満たす製品は、あなたに合った安全な製品だと思われます。 |
|
 |
|
どんな成分が無添加なのかが明確であること。 |
|
 |
|
無添加の成分は、あなたに合わない成分であること。 |
|
 |
|
無添加の成分の代わりに、何の成分が配合されているかがわかっていること。 |
|
 |
|
代わりに配合された成分は、あなたにトラブルを起こさない成分であること。 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
【理由 】 】 |
|
わたしたちは成分の価値を、天然か否かではなく「美しさをストレスやトラブルなく供給できるか否か」で計ります。
なお天然由来成分とは、成分に至る前の「素材」が天然のものであり、素材に化学処理を加えて出来上がった成分です。 |
|
【理由 】 】 |
|
化粧品メーカーが、例えばアロエの絞り汁をそのまま使うことはありません。絞り汁には何らかの工業的プロセスが必ず加わります。
ですからどういう状態が「天然」なのかが、明確であることが必要です。 |
|
【理由 】 】 |
|
例えばレモン汁を肌につけたまま日光にあたると、肌にトラブルが起きる場合があります。
天然のものに工業処理を加えることによって化学的に安定させ、化粧品に配合できるようになります。 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
以下の条件をすべて満たす製品は、あなたに合った安全な製品だと思われます。 |
|
 |
|
そのメーカーが定義する「自然派」の内容が明確であること。 |
|
 |
|
定義がもたらすあなたへのメリットが明確であること。 |
|
 |
|
メリットの内容や理由に対して、あなたが理解・納得できること。 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
【成分の特定ができる場合】 |
|
特定の成分が配合されてない製品を選んでみる。 |
|
【成分の特定ができない場合】 |
|
 |
|
合わないと感じた製品と、合うと感じた製品の成分を照らし合わせ、 |
|
 |
|
2つの製品の成分の違いを見つけて、 |
|
 |
|
合わないと感じた製品にだけ配合された成分を書きとめ、 |
|
 |
|
書きとめた成分が配合されてない製品を使ってみる。 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
【理由】 |
|
薬事法では配合禁止成分・配合制限成分が定められていますが、この規定は輸入化粧品にも国産品にも同じく適用されます。ですので、薬事法を遵守する限りはどちらかが安全(危険)ということはありません。 |
|
【輸入行為と成分の関係】 |
|
薬事法の規定には、成分への規定だけでなく「化粧品の輸入行為」への規定も含まれています。
輸入品については輸入前の時点での成分チェック義務があります。チェックはメーカーではなく、薬事法の管轄にある輸入者の責任で行われます。
この輸入業者のクォリティも、安全な化粧品の流通に大切な役割を果たしています。 |
|
|