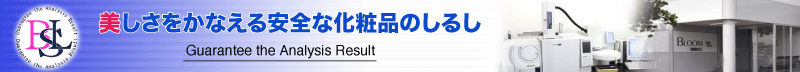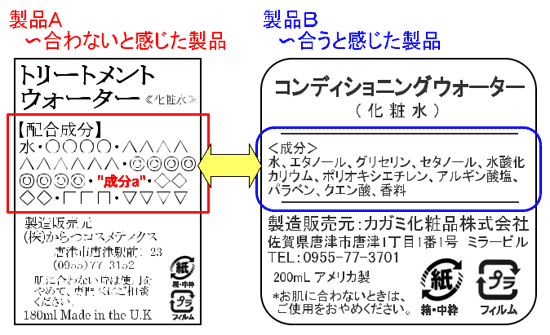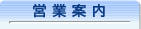 |
|
|
| 化粧品の配合成分表示ラベルと薬事法の成分規制について。 |
|
|
|
|
| 成分の分析方法と検査料金。民間ならではの納期・料金で。 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
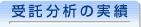 |
| 試験検査の依頼をさまざまな企業や団体から受託しています。 |
|
 |
|
|
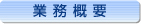 |
|
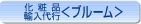 |
|
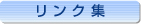 |
|
 |
|
|
| Home > 営業案内 > 消費者の方へ > 「全成分表示」の活用のしかた |
|
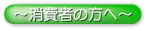 |
|
 |
|
|
|
平成13年/2001年4月の薬事法改正により、配合成分の表示方法は「全成分表示」です。薬事法改正の背景は?改正前の「表示指定成分」とは?全成分表示をどう活用すれば良いのでしょう。 |
|
 薬事法改正の背景 薬事法改正の背景 |
|
|
【改正の経緯】 |
|
|
|
● |
薬事法では従来、化粧品の成分に対する「表示指定成分」を定めていました。その定義は「ごくまれに肌に障害を起こすおそれがある成分」とされていました。 表示指定成分は102(「香料を含むと103」)あり、これらを配合した製品には必ず成分名を表示しなければなりませんでした。 |
|
|
|
● |
この制度は平成13年/2001年3月までありましたが、平成13年/2001年4月からは、原則として化粧品に配合されたすべての成分を表示しなければならない「全成分表示」制度に変わりました。 |
|
|
【全成分表示の目的】 |
|
|
|
大きく分けて、2つの目的があります。 |
|
|
|
|
● |
情報開示 |
|
|
|
|
・ |
表示指定成分であるか否かにかかわらず、「ひとによっては特定の成分に対して肌に障害が起こる可能性がある」という観点によります。 |
|
|
|
|
● |
世界的な流れへの対応 |
|
|
|
|
・ |
薬事法改正以前から既に欧米諸国では全成分表示が主流だったため、日本でもそれに合わせることとなりました。 |
|
|
|
|
・ |
また世界的に見ると、化粧品に配合できる成分の種類が日本では少なかったので、それを緩和するために企業責任(=全成分表示)が求められたという側面もあります。 |
|
|
【全成分表示の活用のしかた】 |
|
|
|
全成分表示の目的に合わせ、活用のしかたも2つ考えられます。 |
|
|
|
|
● |
化粧品選びの基準づくりに活用 |
|
|
|
|
|
自分に合わない成分や、自分が好ましくないと思う成分を特定することで、化粧品選びの幅をいっそう広げることができます。 |
|
|
|
|
|
a. |
成分の特定ができる場合 |
|
|
|
|
|
|
|
特定の成分が配合された製品を使わないようにしてみる。 |
|
|
|
|
|
b. |
成分の特定ができない場合 |
|
|
|
|
|
|
|
 合わないと感じた製品Aと、合うと感じた製品Bの成分を照らし合わせ、 合わないと感じた製品Aと、合うと感じた製品Bの成分を照らし合わせ、
 2つの製品の成分の違いを見つけて、 2つの製品の成分の違いを見つけて、
 製品Aにだけ配合された“成分a”を書きとめ、 製品Aにだけ配合された“成分a”を書きとめ、
 書きとめた成分が配合されてない製品を使ってみる。 書きとめた成分が配合されてない製品を使ってみる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
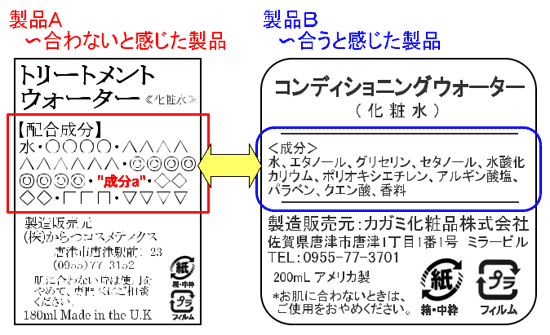 |
|
|
|
|
● |
新製品えらびに活用 |
|
|
|
|
|
企業側の責任のもとで、今まで配合できなかった成分が配合できるようになりました。
近年の例では、コエンザイムQ10/CoQ10がそれにあたります。 |
|